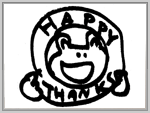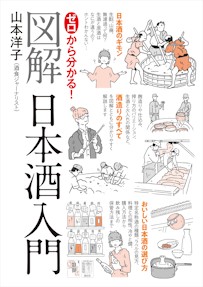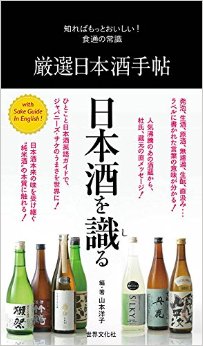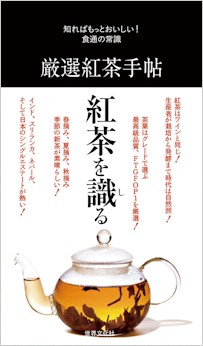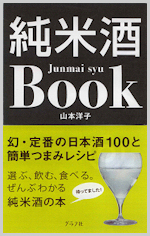ご当地もの
« Previous Entries Next Entries »ジャンクやまよシリーズ その1 たこちゃんのタコ焼き
July 24, 2007「どうしても食べさせたい! おいしいんですよ! たこちゃんのタコ焼きっ」
……ヽ(Д´ ゚)ノ タスケテー
強制連行されたとあるタコ焼き屋さん。ほんまにうまいのかいな。赤色ウン番台の紅生姜入ってるのかなあ…と気乗りせずに店の前。初対面の人には言えません。
「普段はオーガニックなものしか食べないんです」と、すかしたことは (-θ-)ノ
おっちゃん焼いてました。
元気いっぱい、冗談口ずさみながらテケテケくるくる焼いてます。
おんや?
なに? あの茶色い洗面器は
いつのまにかタコ焼きは串にささってる。
うんわ〜〜っ (;゚Д゚)
焼きたてアツアツのタコ焼きをどっぶんつけ込んだ!
タコ泳がしているぅ〜 ヽ(´Д`ヽ)(/´Д`)/
タコ焼きダイビング
できあがりました。
表面しなしな、ジューシィタコ焼き!
一緒に食べた大阪人のM嬢いわく「トッピングが一切ないタコ焼き初めて食べたわ〜。食べたあとの歯のこと考えなくていいんやねえ。こんなタコ焼き初めてやわあ」と感心しきり。
確かに、青のりもかつおぶしもマヨネーズものっていないのは初めて見ました。
温度も下がった串ざしのタコ焼きは確かに食べやすい。ソースのように甘くもない。べたつくものがない。ふむ。
洗面器の中身は醤油出汁。
なんでも「たこちゃん」先代のお父さんが考案したそうです。
店の前には、腰くだけなゆるゆる o┤*´Д`*├o かき氷メニューがありました。
右から2番目の「せんじ」ってなに?
煎茶系かと思いきや
なんと「砂糖水」のことだそうです。
「あれ? そういわへんかなあ」
いわへんで ゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚
地域によってさまざまでしょうが「みぞれ」というのが一般的かと。
やまよ幼少のみぎり都会のゲゲゲの町境港では「ガムシロップ」といっていたかな(ウソでっせ)
「たこちゃん」場所は愛知県瀬戸市内にあり。
市内には2軒あり、ここ「たこちゃん」がおいしいそうです。町の人に「たこちゃん」と聞けばすぐわかるといってました。隣は八百屋さんです。駐車場完備。ベンツのワゴンで行っても余裕しゃくしゃく。
ご当地モノっておもしろい!
ほうじ茶道
July 23, 2007茶色いお茶が大好きです。
焙じたての香ばしいかおりはたまらない魅力。部屋全体がいいにおいに包まれるので、自分で焙じることもよくあります。
そんな話をCRAFT4の片山さんにしたら
「ほうじ茶は出来立てが一番! どんどん味と香りがなくなりますからね。
煎茶手前、玉露手前など、昔ながらの茶道があるのに、ほうじ茶にはないんです。焙じたての味とかおりを楽しめて、お茶にする時間のお手前も楽しんでもらえるよう、ほうじ茶道を楽しむ道具を考えました!」
ほうじ急焼 (ほうじきびしょ)というそうです。
飲ませてもらえるというので片山さんの喫茶店で奥様に、そのお道具で焙じてもらいました。
「ほうじ茶道」のはじまりはじまり。
まずはお道具拝見!
ベージュがかったオフホワイトは耐熱陶土を使用。釉薬は不使用。片山さんの店がある三重県四日市は萬古焼きのふるさとで、土鍋や急須など熱に強い器が得意です。
この急須、使い込むうちに茶渋が染みて迫力が増すそうです。
専用の電熱器をセットして使います。
急須は中もまっ白。
では、教えてもらいましょう! (^O^)
「ほうじ急須を2分間、空焚きにします。熱したところへ茶葉を入れます」
1年以上使っているという片山さんの急須です。貫禄あります。
「4分ほど振りながら、まんべんなく焙じていきます」
じわじわと香ばしいかおりが出てきました。
「玉露や煎茶でちょっと古くなったものも、焙じることでおいしくよみがえります!」
「ほうじ茶が出来たら、熱湯を注ぎます」
ふたは急須を敷く台になります。
香ばしいかおりでいっぱい! 飲む前から飲んでしまった気分です(笑)
焙煎具合が調節できるので、好みのほうじ茶ができるのはいいですね。
いや〜、いろんな道具があるもんです。
思いついたら即、行動に移すという片山さん。
夏のおすすめアイテムは「阪神タイガースの蚊やり!」
あらら、ファンにはたまらないレアアイテムかも!?
喫茶店と蚊やりの問い合わせは片山さんまで。陶芸教室も開催しています。
●(有)片山
〒510-0033
三重県四日市市川原町10-3
電話 (059)332-1144
Fax (059)333-1110
Email touan103@poem.ocn.ne.jp
すりばち館の加藤明子さん
July 16, 2007ごまをすったり、バジルをすったり、すりばちは大活躍! 大中小いろんなサイズを持っています。
こんなにお世話になっているすりばちですが、作っているところを見たことがありません。そこで、日本のおよそ6割のすりばちを作っているという美濃のマルホン製陶所「すりばち館」を訪ねました。
陶芸家であり、すりばち館の館長である加藤明子さん(美人!)にご案内していただきました。明子さんが手にしているのはマルホン製陶所渾身の作、日本最大のすり鉢! 超ビッグです。
「窯と煙突と木造で出来たすりばちの作業場を、21世紀に残したいと願ってつくったのがこの”すりばち館”です」と明子さん。
古いすり鉢や道具が展示されています。明子さんの作品もあり(左端に置かれた見事な壷、大鉢など)
そして、奥へ進むと広い販売室が。元は「モロ」と呼ばれた窯屋の作業場だったそうです。風情あります。
大きささまざまなすりばちは、浅いのあり、深いのあり、絵柄もいろいろで見応えあります!
ありがたいアドバイスもあり。
明子さんがデザインしたすり鉢各種。
「テーブルにそのまま出せるでしょ」
ううーん (≧ω≦。)
ほんとに素敵なデザインがたくさん。
こんなにたくさんのすりばち、一同に見たことありませんから、もぉ、やまよ興奮状態。ヽ(´ω)ノ ダレカトメテ
「さあ、作業場へどうぞ」
は、はい、はい、はい。
マルホン製陶所は、ここ美濃の地で、明治43年に創業。
伝統の技は今もしっかり生きてます。すり鉢は成型後、職人さんが丁寧にくし目をたてていきます。ここが勝負の見せ所。確実に早くがモットー。
乾燥した後、700度で素焼きします。
その後、釉薬をかけて本窯で1230度の高温で焼成されて、ようやく完成となります。
十草という柄の絵付け中です。
うちに持ち帰ったのは(写真右)片口の茶十草、(写真左)片口の深鉢タイプです。何度見ても、ほれぼれ。
山水画、文字などを呉須絵具で手書きしたものもありました。明子さんいわく「絵柄、大きさともに特注も可能!」だそうです。
うぅ。すりばちを引き出物にしたかった。次回はそうしよう(うそうそ)。
深鉢に煮物を入れてみました。
なんてことない田舎の煮物ですが、すりばちのおかげでどっしり感が出ました。
十草柄にはごまあえを入れました。
炒りごまもスイスイすれて使い勝手抜群!
すりごまに味噌、みりん、豆乳を少々入れてさらにすり、ゆでたインゲンをからめました。茶色のストライプがごまあえに表情を与えるようです。
一生使いますね。明子さん。今度は小さいのを買いにいきます!
〒509-5401 岐阜県土岐市駄知町2321-55
マルホン製陶所 「すりばち館」
開館日 金曜、土曜、日曜のみ(月曜〜木曜は要予約)
開館時間 10〜16時
電話 0572−59−8730
FAX 0572−59−1961
赤米の田植えをしました!
July 3, 2007先週の金曜日、休みをとって赤峰さんの農場に行ってきました。ここはやまよにとって「聖地」なのであります。
赤峰さん、キュウリの誘引作業中。1本ずつ、ふんわりした布でやさしく結んでいきます。布はハンカチ工場からもらってくるそうです。
「ビニールに比べて、野菜にも優しいし、自然に帰るしな、ええんよ」
夏野菜は成長が早いため、スタッフの皆さん、フル回転で作業中。朝は太陽とともに、そして夜は22時まで畑で作業という目の回るような忙しさ。
畑のあいまに塩場見学に行ってきました。
なずなの塩場です。天日ハウスの中はなんと50℃! 普段、会社で地獄のような冷房生活をおくっている冷え冷えBODYのやまよにとって ここはパラダイス!!岩盤浴以上の効果が一瞬であらわれました(笑)
冷え性の人は塩やさんで働くといいですね。やまよも真剣に考えてしまいました。
「今晩は雨がふるけんな、その前に芋の苗植えらんと」と赤峰さん。
出荷作業をこなし、きゅうり、茄子、夏人参の畑仕事のあとは、芋畑へ急いで移動してます。この時点で夜の7時すぎ。
「こ、これから植えるんですか?」
「そうよ、今日はちょっとしかないけんな」
作業はちょっとと聞いていたけど、畝がずらずらずら〜〜っとお待ちかね。これでちょっと?! 恐るべし。
作業を終えた赤峰さん「明日の朝は田植えじゃ」
ラッキー! ヾ(^▽^)ノ
田植えに参加させてもらいました。
フォームが見事に決まっています!
早い、早い赤峰親方。踊るような早いリズム!
かっこだけは一人前のやまよ。
右手に持つのが赤米の苗、左手は田植えのガイドライン棒です。縦線、横線を決めて植えていきます。
どうみてもへっぴり腰。。。あともう少しの図。仕事が遅い。。。
赤峰さんは、やまよの10倍の早さで田植えをこなし、次の畑へと風のように去って行ったのでありました。
田植えしたあとの手はすべすべ! 栄養たっぷりのなめらかな泥が効いたんですね。
田植えのあとは後藤さん、山崎さんの手作り料理がお待ちかね。玄米おむすびの中身は、しそ味噌や梅干しなど4種類あり。食べるときに海苔を巻きます。飲み物は三年番茶のホットとクール。タッパーにはなずなの塩もちゃんと。
絶品! キュウリの酢みそあえ
茄子のステーキ。
どちらも作り方は「百姓 赤峰勝人の野菜ごはん」に載ってますよ!
↓おまけ
赤峰さんのところに行くときは、大分空港からいつもレンタカー。お気に入りはトヨタのヴィッツ。小回りきいて、上り坂もきびきび走り、なんといっても燃費が抜群、車内も快適。コストパフォーマンス最高です。今回もありがとう!
畑の入口にて。
40年前にタイムスリップする雑貨店
June 28, 2007その昔、買い物といえば「買い物かご」を持って行くのは当たり前でした。ビニール袋なんてありませんでしたからね。
JR大垣駅近くを歩いていたら、どどーんとモノモノモノにあふれるお店を発見!
な、なつかしいアイテムがずらりんこ!
なんと40年前のスリッパ掛けを発見。
特売中で980円。いつから特売中なのかは不明。。。
あ〜〜っ。夏おひつ、境港の実家にもありました。ありましたとも。
よく見ると、下には40年前のものという木製おひつが〜。
おぉ。木製の蠅帳、45年前のものとあります。特価中 3980円也。
ひぇ〜。鼻血でそうでうす。アルミの万能片手鍋。
こちらも40年前で780円。赤字の文字が消え入りそう。その下のたらいは琺瑯、金だらい。
お店全景。
ここだけタイムスリップの図。
風鈴から日よけ帽子、お弁当箱、風呂椅子まで、ありとあらゆる種類のものが渾然一体! これが本当の雑貨店ですね。
ビニールがかけられたところは、まるで前衛アート。
掘り出しもの多々あり(しかし、棚卸しはどうしているの??)の雑貨店。
絶滅寸前の生活道具に出会えること間違いなし。
某古道具店より格安に(適正価格?)で購入できましょう。
場所はJR大垣駅を背中にし、まっすぐ大通りを歩いて左手にあります。ついでがあったらのぞいてほしいお店です。
陶の国へ行ってきました
June 22, 2007陶の国ってどこ? やまよも知りませんでした(^^;)
日本の焼き物の出発点である東海の4産地、瀬戸焼、美濃焼、常滑焼、萬古焼(日本の8割の器はここで生産)が、いいもの作りのために共にがんばっていこうと連携し「陶の国」と名づけたそうです。
最近、安い中国製品の輸入が増え、この4産地は、どん底まで生産量が減っているとか(T_T)
うーん、聞き捨てなりません。いったいどうなっているのか、4産地に出かけてきました。
型から出たばかりの食器さん。素焼き前に天日でじっくり乾かします。なんとも気持ちよさそうな風景。
落ち込んだというアイテムの中でも、とっくりの数字を聞いてたまげました。
美濃焼きのカネコ小兵製陶所の伊藤さんによると
「昭和50年代は月に10万本生産していたんです」
Σ(・oノ)ノ ナント
10万本! ひと月にですよ。それだけお燗酒を飲んでいたということですね。思えばそのころはお酒といえば日本酒で、お燗するのが当然でした。「貧乏人の冷や酒」なんていう言葉もあったほど……。
それが今や
「月に2000~3000本でしょうかね」
激減。。。
とっくりの町には、どでかいとっくりのモニュメントもあり。
さて、こちらは常滑。伝統的なかめもモチロン健在。常滑のかめは戦国時代、篭城するときの必需品で水がめとして大活躍。水がおいしくなり、また、 腐りにくいそうです。海路で全国に出荷されたとか。今は焼酎メーカーや、酢メーカーが購入。う~ん、欲しい。置く場所はないけれど。
山文製陶所の山本幸治さん、気になるお値段は?
「軽自動車くらい!」
オオモノが得意な常滑では、陶器のお風呂にも力を入れています。
茶碗に見えるので、高山陶園の渡辺さんに入ってもらいましょう。
いったいいくらなのか恐る恐る聞きますと、
「型ものなら60万円代から」 大きさからいうと超安! (しかし、こんな大きな型があるというのもすごい)
「手びねりだと200万円くらいから」
手でコツコツ作って焼いて、気が遠くなりそうな作業のことを考えると、良心的な価格だと思います。
「山本さん、別荘にひとついかがですか?」
べ、べっそう建てることがあったら真っ先に考えます。
お問い合わせはとこなめ焼協同組合まで
屋根の上でも天日干し。こちらは瀬戸焼き五春窯・加藤克己さんの工房です。
ひきこまれるような存在感のある120年前のたぬき殿。
四日市、萬古焼の里・藤総製陶所・藤井さんの庭に鎮座してます。非売品。
織部あり、呉須あり、焼きしめあり、そして直火OKの耐熱器ありで、魅力たっぷりの4産地。
この地で見つけた使い勝手の良い器をおいおい紹介していきます。つづく。
新発田名物!笹だんご&ちまき
June 14, 2007わ〜、今年も届いた! 新潟の高澤大介さんから地元の自慢の逸品が送られてきました。箱を開けただけでぷ〜んと笹の青い香りがただよいます。まるで青畳の上に座っているみたい。
日本のラッピングの技術たるやすごいもんだ! と毎年感激させられます。よっしゃ包み方を覚えようと1枚ずつ丁寧にはがして感心するものの、すべてはがしてしまうと、再現不可能 ヽ( ~д~)ノ 難しいです。
中身のよもぎ餅には、ご覧のように笹の葉のあとがくっきり。中には甘いあんこが入ってます。
じつは、やまよのお目当ては (*^-^) 笹だんごじゃなくて
こちら!(゚∇^d) !!
ご存知ですか? 笹の葉にくるまれた「ちまき」さんです。
甘いものがあまり得意でないやまよには、高澤さんがこちらも入れてくれるのです。おじさんの心をよくご存知で(笑)
ちまきの見事なラッピング術。ほんとに素晴らしい。
まさに、実用の美!
結び目をほどき、葉を一枚めくると、じゃじゃじゃ〜ん 中身の登場です。
なんと、もち米だけ。
そんな潔さが好き。
葉をめくるたびに、いい香りがぷ〜〜ん。食べる前から、笹の香りで幸せ気分。もち米に自信があるのでしょうね。さすが米どころ。
別添えのきな粉で食べるようにと書かれていますが、このままも美味、焼いても美味。
高田屋さん、玄米のもち米で作ったものも食べてみたいです(笑)
新発田の老舗・高田屋のご主人によると、笹だんごとちまきは、もとは節句のお菓子だそうです。
「節句はこのあたりで は6月でしてね、4日は笹だんご、5日はちまきを食べます」とのこと。
2日間にわたって、2種類を食べるんですと。笹の殺菌力に注目した昔の人はすごい。そして香りはゴチソウですね。
ご主人に味の秘密を伺うと
「やっぱり、米ですよ! うちは”こがねもち”を契約栽培してもらってます。笹は村上の山の笹。だんごには羽二重粉、新粉などをブレンドしてね。材料にはこだわってますから!」
ちまきは前の日に笹に包んで、うるかしておき、翌日2時間かけて煮るのだそうです。
「戦国時代、笹の葉にくず米包んでちまきにしたという話もありますよ。昔の人は頭よかったね!」
笹だんごもちまきも、10個ひとしばりで1050円。
良心的価格! 高田屋さん、いい仕事されてます〜。
笹だんごはほぼ通年、ちまきは4月〜6月末までの期間限定販売。地方発送OK。送料別。
ほかのお菓子作りもあって忙しいので、笹だんごはお休みする時期もあるとか。注文するときは、お電話で確認してくださいね。
●高田屋
〒957-0058
新潟県新発田市西園町1-1-5
電話 0254-22-3368
fax 0254-26-8824
裏話。
葉が青々しているのは生の笹の葉だから。じつはこれ、高澤さんがやまよをぎゃふんと言わせるためにわざわざ特注しているそうです。高田屋のご主人にそのことを聞いてビックリ仰天。高田屋さんでは、通常、一番い い時季に採取した山笹を乾燥させて使用しているそうです。「冷凍品は使いません」とのこと。乾燥葉は自然乾燥でこれまた自信作!
幻の碁石茶
May 28, 2007有楽町「青空市場」へ。発起人の永島敏行さんもジャンパーを着て、よく通る素敵な声で呼びかけをしておられました。千葉から能登から、各地の生産者の方が集まって、なかなか楽しい。高知県の碁石茶に出会いました。
碁石茶、飲ませてもらうと、すっきりして、ヘルシーなやさしい味。何杯でも飲めそうです。 珍しい「後発酵茶」で、茶葉は蒸した後、もまず、ムシロをかけて寝かしてカビづけ。さらに杉桶に入れて重石をかけ、また漬け込むと!いう二段階発酵茶。それを四角くカットし、天日で乾燥させて出来上がりという手間と時間をかけたもの。
茶はこの地で自生している山茶とヤブキタをブレンド。山の急斜面で栽培するため重労働なんだとか。
もとは、東南アジアの山地で生まれた製法、なぜ四国山地に伝えられたとかは不明。不思議ですねえ。
そしたらこの碁石茶、私が知らないだけで(笑)とっても有名だったのです。検索してみたら、出てくる出てくる。値段もさまざま(市場では50gで840円で販売)。なんとニセモノまであるんだとか。
組合長・小笠原さんによると昭和50年代は絶滅寸前で、作り手がたった1戸まで減ったものの、いまや9戸に復活。「本場の本物」という認定も受け、復活運動に応援団も多数。
がんばって! 「大豊の碁石茶」。
見つけたらぜひ、飲んでみてください。日本はまだまだ広いなあ!
家で入れて飲んでみました。乳酸菌を多く含んでおり、酸味があって、花のような、高菜漬けのような良い香りがします。二日酔いでもスンナリ入るまろやかで、すがすがしい風味。中国茶好きの人ならたまらないかも。茶粥にするとおいしいというのもわかります。
なぜ、碁石か?
仕上げの天日干し風景を遠くから見ると、碁石を並べたようだからとのこと。見てみたいですね。
からほり通りのこんぶ 土居さん「日本一のだしのとり方教室」開催
May 18, 2007
「心地いい暮らしがしたい 素食がおいしい。vol.4」で昆布のイロハを教えていただいた大阪のからほり通り商店街にある、老舗の昆布やさん「こんぶ 土居」。
なんと、だしのとり方教室を始めたのだとか。人数は6名(2名ひと組で3組限定)。受講料は230円(なぜ、230円かには深い意味が)。先生は土居純一さん(独身!)と、お父さんの成吉さん。
日本一の昆布、正真正銘の天然の真昆布です。しかも特級クラスの川汲浜のもの。葉肉も厚く、幅も広い最高級品。色もややあめ色がかったほんまもん。上品なうまみと甘みがあり、澄んだだしがとれるという品です。
昆布の力を最大限に発揮させるために大事なことは
「昆布は乾物。かならず水でしっかりもどしてください。真価が発揮できません。2時間。できればひと晩もどすと最高のだしがとれます」
せっかくのいい昆布でも、力を出しきらなければモッタイナイ! 昆布は乾物だってこと、改めて肝に命じるの巻。
こんぶ 土居的「日本一のだしのとり方」
昆布+鰹節のスタンダードなだし
水 1リットル
真昆布10〜15g
鰹節(昆布と同量)
自然塩2〜3g
ひと晩つけてぷっくりもどった真昆布を、つけた水ごと弱火にかけます。沸騰したら火を止めて昆布を取り出します。
「いい昆布なら少しくらい煮立てても大丈夫です」
取り出すと、こんなに大きくなっています。ビッグショック。「あとで佃煮にしてください」 はい!
このあと鰹節を入れ2〜3分おいてすばやく網でこします。温度が下がった分、もう一度火にかけ、塩を2〜3g加えます。
「はい、完了です」
出来ました。なんと早い。日本一のだしなのに、あっというま!
「フランス料理だとこうはいきませんね(笑)」
きれいに澄んだ出来たてのだし! 美しい〜。
さて、試飲。
つーぃ。おぉ、すこぶるうま味が濃い。濃すぎるほどです。じつは、塩を入れる前にも試飲しましたが、塩不要というくらい味充分でした。ですが、塩を入れて飲んだら、これまたピシリとしまって完璧。
さっそくお椀に注ぎます。
「いいだしなら、具は三つ葉や麩くらいがいいですね」と純一さん。
「和食の1万円のコースに出されるだしと同じですよ。いや、それ以上のコースなのかもしれません(笑)」と成吉さん。
「好みですが、醤油を香りづけ程度に1〜2滴落とすと、味が丸くまとまります」
ぽと、ぽとり。つーぃ。 おぉおおぉ。本当です。
こんぶ土居さんからのone point*
「品質の良い昆布や鰹節なら、温度や抽出時間にあまり神経質になる必要はありません。もし、雑味の出やすい原料を使用する場合は、少し低めの抽出温度にすることですっきりとした味のだしがひけます」
店内にはありとあらゆる昆布で一杯。真昆布の種類もさまざま。日本橋の高島屋でも買えますが、本店でしか買えないレアなアイテム多し。
細切りしおふき、刻み昆布、こんぶあめなどオリジナル製品も数多く、目移りしてしまいます。中でも25年ほど前に作ったという人気の品が「帆立と昆布の 柱こんぶ」。
北海道南茅部産の天然真昆布と天日干し天然帆立貝柱を、醤油、酒、みりんで味つけた逸品です。最近、類似品が出たそうです。
「内容を真似してくれるならいいんですけど」と残念そうな成吉さん。
アミノ酸や酵母エキスなどで人工的に味つけした食品が多いことに危機感をもっている土居さん。それぞれの商品のパッケージに詳しい原材料と、ものによっては割合まで事細かく紹介されています。
「真似してもらえたらええと思って」
えっ!? !Σ(▼□▼メ)
柱こんぶの袋を見てびっくり仰天
「醤油17.6g(大豆・小麦・塩)、昆布16g(道南産天然真昆布)・帆立貝柱8g・酒4.3g(米・米麹)・みりん4.3g(もち米・米麹・米しょうちゅう) 内容量40g
ここまで書いてある商品なんて見たことありません。
さて、230円の講習料のナゾを聞くと
「使った昆布と鰹節と塩の実費です」 なんとっ!! (^^)b
230円あれば、最高級のだし1リットルがとれるという意味なのだそうです。そんな手軽な贅沢!してみたいですね。昆布さえもどしてあれば、あっというま。スタバのコーヒーより安い日本一のだし。おうちでゆっくり味わってみませんか?
・「こんぶ 土居」さん料理雑誌「四季の味」夏号(6月発売)で紹介されるそうです。要チェック!
●こんぶ 土居
大阪市中央区谷町7−6−38
電話06-6761-3914
FAX06-6761-7154
*谷町六丁目駅 4番出口を右に進み、からほり商店街を入って左側にあります。
営業時間 9:00〜18:00
日曜祝日定休 夏期、年始休み
高菜の花って美味!
May 14, 2007連休に実家に帰ったとき、父の畑の高菜は花が咲いた最終段階でした。母が漬けた花の漬け物があまりにおいしかったので、やまよもごっそり摘んで帰りました。高菜は 葉を食べることがほとんどですが、花と先端の茎の部分は生でもいけます。畑では収穫も忘れ、ぽきぽき折っては口に入れて遊んでいました。
こういうの自家栽培の醍醐味ですね。
摘んでから1週間たったというのに(もちろん冷蔵庫で)、シャキシャキシャキーンとしてます。
いい塩をきかせた熱湯でゆでたところ、なんとも美味! 高菜の甘みとさわやかな苦みのバランスが抜群で、味が凝縮しています。
農薬を使わないで栽培した野菜は、味はモチロン、もちが違うとあらためて実感。こういうときは、上等なオリーブオイルくらいで充分ですね。
じつは収穫したほとんどは漬け物名人の義父にドカンと送りつけました。
べっこう色の漬物になって戻ってきました(笑)
作る父と漬ける父がいて、ダブル父のコラボですね
\(^_^ ) ( ^_^)/
二人とも巳年の78歳。長生きを心から願うやまよであります。