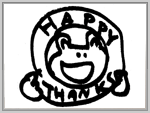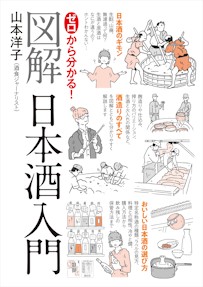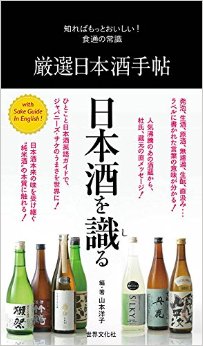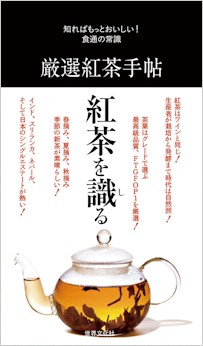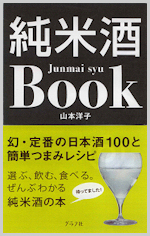ご当地もの
« Previous Entries Next Entries »岡山・稲刈りツアー2 いざ蔵元!
October 14, 200810日の夜、地酒応援団の「どんたく」で岡山のお酒のお勉強
予習を兼ねて丸本酒造の「竹林 瀞(ちくりん とろ)」、そして御前酒「雄町純吟生原酒」
丸本酒造の「ふな口」、大典白菊の「白菊米」。どっしりしたタイプが多いですね。
翌朝、岡山駅にて。目指す鴨方駅は倉敷から4つめ。26日は知事選。
のどかな山陽本線。cafe8の二人は初めての路線。車窓からは青い田んぼ、小屋が続きます。
鴨方駅到着! お昼はかもがた町家公園で温かいお素麺をいただきました。これで400円。町のボランティアさんが手作りする真心の味。
鴨方は素麺の町。飛行機で参加のひるちゃんも合流し、秋晴れのもと、素麺をアウトドアで。そしていざ、蔵へ!
左)丸本さんの奥さまがお茶を一杯。右)飼い猫の「ぎん」ちゃん。うちよりも広い縁側にて。
いよいよ田んぼへgo! 黄金色にたわわに実った美しい稲穂が広がります。丸本酒造の田んぼは全部で9.5haあり、あちこちに分散しています。
そのうちの50aが有機JAS認定の田んぼです。
そして「丸本酒造、オーガニック史上、最悪の田んぼになりました」と丸本さんが嘆く田んぼへ。
おや、あたり一面、黄金色……とはほど遠いブラウン系。なんでも田植え直後に水切れを起こし、あらゆる草さんの種が定着してしまったそうです。除草剤は一切使わないため、水の管理が何より重要だそうですが、ちょっと目を離したすきに……こんな失敗もあるそうです。
しかしこれほどまでに草に占領された田んぼも珍しい! ある意味、見ることができない新鮮な光景です。
去年のオーガニック田の稲刈り風景。田んぼの場所は違います。
草というのはヒエやら草ねむやら。中でも厄介なのが草ねむで草というより木質化した「木」。これがコンバインに入ると刃が痛んでしまうとか。これを抜く作業をお手伝いすることに。合歓の葉に似ているから草ねむというらしいです。
有機JAS田なので、必要書類をチェックして作業を進めます。田んぼに入る前に足下を清水で洗い、他からの土が混入しないようにします。丸本さんは素足で田入り。いつもだそうですが、痛くないのか不思議。慣れると平気だそうですが。
草ねむくん。意外にすぽっと抜けます。抜いたら砲丸投げよろしく、集積場まですこーんと投げ飛ばします。この作業、結構、快感!
草ねむはカワラケツメイにそっくり!同じ品種かと思ったら違うようです。とあるかたのHPよりLOOK
しばし草とり作業のあとは別の田んぼで稲刈りに。コンバインに乗車。
こちら、たわわ系の田んぼ
たわわ系田んぼ残り一列の図。フィナーレ!
最後の一列を刈るカワムラさん。右)たわわ系の稲穂。
そして、ブラウン系の田んぼに戻る。草取り隊のみなさ〜〜ん、やってますか〜? 「はーい!」 あ、かなり進んでいます。
手前は草取り後。後ろは草取り前。田んぼの色が違います。
つづく
岡山・稲刈りツアー1
October 14, 2008快晴の連休! 岡山県の蔵元、丸本酒造へ稲刈りに行きました。2003年に酒米農業特区の認定を受け、自社田で山田錦と雄町を栽培。その一部は有機JAS認定を取得し、トレーサビリティが確実にとれる安心安全な酒米づくりに励んでいます。
ワインのシャトーがぶどうを栽培して醸造するのと同様に、米を育て、酒を醸すという一貫した日本酒づくりなのです。
6月に田植えにいきました。その稲を刈りにいったのであります。
秋の丸本酒造。奥に見えるシルバーの瓦屋根がお蔵です。
じつは、行く前から準備万端!
今回はcafe8のキヨノさんカワムラさんも「日本の米と酒を勉強をしたい!」と一緒です。待ち合わせは東京駅グランスタのはせがわ酒店。Barでは羽前白梅を注文。
岡山といえば雄町なので、雄町米の勉強のために醸し人九平次(日本酒デモの発起人)をいただく。
連休前日のコミコミ新幹線のぞみ車内で九平次の後は、タスマニアのピノノワールを飲むすっぴんトリオ。
そして岡山駅に到着! 明日から稲刈り。早く寝て明日に備えようと!いいながら町へ繰り出す我々であった。つづく。
これから
October 10, 2008読みづらいですね。企画だおれ!?(笑)
これから稲刈りにいってきます!
名古屋の夜
October 9, 2008出張があった月曜日、名古屋に泊まることに。久しぶりです。名古屋の夜!
名字に魅かれるせいか!? つい立ち寄りたくなる「山本屋本店」。味噌煮込みうどんの土鍋のふたは穴なしで、取り皿を兼ねてます。販売もしていますが(通信販売の項、参照)高すぎっ。100年持つと言われてもねえ。
名物、山本屋のお替わり自由のお漬け物(塩が少々キーンと辛いのが難)。とはいえ、生姜のすりおろしが外出先でいただけるのは非常に嬉しい!
トヨタビル・ミッドランドスクエアには、DEAN & DELUCAあり、バカラあり、インタッチあり。裏口には自転車の駐輪場が扉つきであり。
少し歩けば究極の居酒屋あり。ビルの谷間に古い鶏店あり。
呼ばれているような店「世界の山ちゃん」。入ったことありませんが、”味噌ラガー”なるビールがあると聞いてます。右)服飾雑貨店なのに硝子工事OKの店もあり。
「くねくねラーメン」あり。近代的ショッピングビルあり。新旧、混在。
さて、今宵のお目当ては
「出雲」の大谷しげさんのお店。この春、移転して新しくなったものの行く機会なし。そこで突然行って驚かせてみました。「なに、なにどうして〜〜〜!?」としげさん。店はまだ三分の一しかできていないそうです。確かにそんな感じ(笑) 塗り壁は鳴門の漁師、村 公一さんが「おもろないから」と「海」をイメージして手でひっかいてくれたとか。
その村さんの鱸。「村さんますます進化して、この鱸は2週間たってるんです」そんな古い魚だすんかいな〜。「エラがピンクでしょっ」
左)2週間めの鱸の刺身。 右)3週間め!の鱸の刺身。なるほど悪くはない。昆布〆のような雰囲気です。「こんな風に味が良くなるのは、村さんの鱸じゃないとありえんです」
鱸の皮の塩焼き。2週間めの鱸の塩焼き。
「焼き物の骨はお椀に入れてください」
大根を昆布だしで煮たという鍋を持ってきたしげさん。骨の入ったお椀に汁を注ぐ。余計な味付けがない、クリアな味。
マクロビオティックの考えが好きというしげさん。ごぼうは皮つきのまま。砂糖は不使用。
鱸をフライに。ブロックのまま揚げて、中まで火を通さずに仕上げ、身のグラデーションを楽しむ。
あと三分の二完成まで、地道にがんばってね!しげさん。研究もいいけれど、やりすぎに注意(笑)
日本酒はごとう屋、後藤久彰さんから届く久保本家、神亀酒造が揃っています。
ありがとう、名古屋の夜。
名ではなく味で勝負の品揃え 鳥取・谷本酒店
September 26, 2008お店屋さんみたい! 箱ワインを購入。先日お邪魔した鳥取市の谷本酒店さんで発見。これは谷本さんの直輸入ワインです。
「一般に想像する箱ワインとは味が違います! ブラインドするとまずこの値段だと誰も思いません」
鳥取市生まれの佐藤央さんという女性がこのワインに惚れ込み、イタリア人のご主人と共にこのワインを売る店をフィレンツェに開いてしまったのだとか。市内在住の佐藤さんのお母さんからじきじきに売り込みを頼まれた谷本さん。「買ってあげたいですが、おいしくないと買えません。とはっきりいいました。それが飲んでみたら!!」
これで5リットル。「赤は特におすすめですね。サンジョベーゼならではのコクがあります。楽しめますよ〜」
ある意味、スーパー(な)トスカーナ!?
東京の老舗デパート、T島屋に勤めていた谷本さん。鳥取に戻り家業をつぎました。「斜陽産業の酒屋でしたから、違うことをしないといけないと。美味しいものは名前ではなく、味と言うのが自分のポリシー。お客様においしいものをお手ごろ価格で手に入れて頂いて、本当に美味しい!と叫んでほしいから酒屋をしている変な店長(笑)です」
とはいえ銘醸ワインの品揃えも見事。
ブルゴーニュ充実。もちろんミュジニーも。
アルザスのピノノワール、自然派ピノノワールもあり。アルザスは特におすすめとのことで購入。
ふふふ。
多種多様の銘柄ワインを飲み込んでいる谷本さんだけにその言葉は信頼できます。また、鳥取という地方でがんばっているから努力もいっぱい。
で、この箱ワインはなんと5リットルで3570円! 興味しんしんで買ってしまいました。
谷本さんを信頼するきっかけはじつは日本酒から。なんと大好きな神亀酒造のお酒が冷蔵庫の棚を占領しているのです。ときどき蔵元の小川原専務もいらっしゃるとか。
大古酒 ひこ孫「時のながれ」
これが置いてある酒屋さんは、全国でも数少ないと断言できます。蔵元との信頼関係があってこそ。
冷蔵庫の4段すべてが神亀の酒。蔵元さえも心配したという(笑)ほんとに変な店長!
説明もしっかりあります。写真右は郷土の酒、鳥取の地酒コーナー。鷹勇、日置桜、諏訪泉などなど。強力米使用の酒も充実してます。
世界のおいしい地ビールあり、焼酎あり、酒の肴あり。広々して買い物しやすい店内。県の人口が60万人をきってしまった鳥取県で大丈夫なの?という品揃え。最近、ネットショップを始めたとか。例の箱ワインは福岡のレストランから注文が繰り返しきているそうです。ネットは地域を越えますね。楽しい時間はあっというま。実家に一瞬帰るために谷本酒店をあとにしました。駅まで5分。
スーパーまつかぜに乗ると1時間で米子へ到着。意外に早い。そして境線で境港へ。
翌朝、9時米子空港発の飛行機で東京へ。
珍しく兄が空港まで送ってくれたのでパチリ。
びゅーん。米子からはB737-500。客室乗務員さんが救命ベストを着てみせてくれるタイプ。
翌日
到着! 箱ワイン。
かんぱ〜い。確かに色も濃い、味もある。サンジョベーゼ久しぶり。
外食が続いたので野菜ばっかり! ナッツ感のある菜種油や、にんにく、生姜、ハーブ、シャンパンビネガーをちょこっと使って赤ワインにあうようにしてみました。家のごはんはほっとします〜。
ワインラックを取り付けました。既製品ではちょうどいいサイズがなく、金物屋さんに作ってもらった特注品です。とっても便利! たまに頭に当たるけど(笑)グラス越しで見るキッチンの風景、ちょっぴり変化がでました。
鳥取の海の幸、野の幸
September 25, 2008
びゅーん。
B737-800で快適なフライト。
大量の燃料を使う飛行機はCO2もたくさん排出。国際線の長距離機になると一度に10万リットルもの燃料を使うとか。飛行機に乗るからには意味ある移動にせねばと思います。
9月の全日空寄席は、いとし&こいしの漫才が。「子供物語」初めて聞きましたが、神田紅さんが絶賛するのも無理がない!完成度の高い話芸に聴き惚れてしまいました。大人になってわかる芸の技術。
そうこうしているとあっという間に鳥取空港。木村Kさんがお迎えに来てくれました。同じ飛行機だったT氏と一緒に空港近くの「かろいち」へ。
かろいちは「賀露港(鳥取港)で揚がったばかりの魚をイの一番に販売飲食する海の市場」。活気あります。赤イカでかっ!
「観光客というよりも市民が買いにきている。それがいいんですよ」と木村さん。
白ハタも赤カレイもひと箱500円。ワンコインあれば当分食べられますね。魚価安すぎ。
アジはこれで200円。
かろいちには鳥取JAいなばの直売所もあり。
乾燥そら豆150円。
乾燥まいたけ350円。
はま茶200円。
昔からこのあたりで飲まれていたお茶「はま茶」も購入。弘法大師が飲んだという言い伝えもある健康茶で植物名はカワラケツメイ。特有の香ばしいにおい、ほのかに甘く、さっぱりした味が特徴。カワラケツメイはマメ科の一年草で本州、九州の原野や川原に自生。夏から秋に黄色い小さな花が咲き、ミニチュアのサヤエンドウみたいな豆ができます。
そんなカワラケツメイを洗って干して丁寧に炒ったものがこのはま茶。120g入ってたったの200円(涙)。JA通してこのお値段。安すぎませんかねえ。気高町の山本美津子さん作。おいしくいただいてます。
宮崎 台風でもう一晩
September 25, 2008先日の北郷町の続きです。写真はひと晩お世話になった合歓のはな。人里離れた静かな土地に建てられた宿で、全室が離れという贅沢なつくり。
一部屋ごとに露天風呂があります。
お風呂の脇に網があり、簾で蓋をしている理由は「葉っぱや蛙!が遊びにくる」ことから。自然の中ならではの備品です。
合歓のはな料理長、宮田恭富さんの創作料理。宮崎県のシルエットという石の上に珍味がずらり。お酒を飲め!といわんばかり(笑) 宮田料理長は生姜のはじかみのピンク、ラディッシュで彩るのが好き。ちょっとlovely
焼酎文化圏における日本酒のラインナップとは
黒龍、阿部勘とすっきり系から、菊姫 えっ?王祿の丈径が。しかも生原酒。酸度2.1の濃熟系ですからね。どうなんでしょう…といいながらぬる燗で。
カウンターに移って食後酒を。社長自ら腕をふるいます という甘いカクテルをすすめられましたが、甘いのが苦手なやまよ。地酒をいただきました。郷に入れば郷に従え。
その翌日、ホテル北郷フェニックスで会がありました。お昼近くになると予報どおり台風が直撃
激しい雨で外の景色がまったく見えません。乗る予定だった16時発の便の欠航が決定。町で一番の高台にあるこのホテルでそのままお世話になりました。
昼食で出されたデザート。黒豆を堅めにゆで、柿はメープルシロップで甘味をつけたもの。黒豆本来の味がよくわかります。ハーブは自家栽培とか。
深水政信料理長。お子様がアトピーで食事制限をしているそうです。どうりで食養にもお詳しいわけです。料理長も雨のため、帰れずじまい。
そうして夜はふけてゆき
翌朝は、台風一過!
去ってしまうとあっけらかんと快晴。洗い流されたあとは、美しい光景が広がります。
宮崎 森林セラピー基地*猪八重渓谷
September 21, 2008宮崎県北郷町の猪八重渓谷へ行きました。
原生林の中を歩くと、滝が次々に現れる森林セラピー基地です。
台風がくるという雨の中、カッパを着て散策。すると…
道の真ん中でお出迎えしてくれたウシガエルさま(たぶんウシガエルだと思うのですが…)。土や落葉した葉っぱと同系色。近づいても微動だにせず。自分の道を邪魔するなと言っているのかもしれません。
どうも!お邪魔してます。
「……。」
雨のおかげで葉っぱが洗われ、つやつやときれい。葉や苔の先に雫ができて、それは美しい光景です。植物の匂いも雨のおかげでしっとりしています。久しぶりに自然の中を歩いて身体も大喜び!
赤、白、茶色とキノコもいろいろ。たぶん毒キノコですが、蛙の椅子みたいで、とってもかわいい!
だんだん水かさが増してきてます。倒木が流され、ひっくり返ってささってます。
お出迎えしてくれたウシガエルさまの後ろ姿。堂々たるものです。 また会えますように!
飫肥杉で有名な北郷町。道に飫肥杉のチップを敷き詰めた道が。踏んだ感触がやわらか、自然にふんわり沈み、歩くたびに気持ちいいのです。そして杉のいい香りでいっぱい。逆に靴がきれいになる(!?)ようでした。
次回は晴れた日に!
新潟 雲洞庵の土踏んだか
September 14, 2008鶴齢さん近くにある「雲洞庵」は、室町時代に開創された庵寺。この赤門も室町時代に建立され、江戸時代に再建されたという歴史ある門。その昔は皇室や大名などの来訪時と、1年に1回開けるのみだったとか。
本道までつづく石畳の参道。これが噂の!
石畳! 一石の裏に一字ずつ法華経が刻まれているとか。踏みしめてお参りすると、”罪業消滅、万福多幸の利益にあずかる”と。ありがたいことから「雲洞庵の土踏んだか」と修行者が言い合ったといわれています。でも土? 石じゃなくて。
「踏みつけても利益を与える、佛教・禅宗の教えは寛容そのものです。それが日本人の心となりました」なるほど〜。
なるほどなるほどと、うなずいてシャッターを押す越七の藤井さんであった。藤井さんは昨年、脳梗塞で入院。無事、快復!し 13kgやせてすっきり元気に。ただし太るの厳禁の病のため、今の体重を死守すべく食事は肉ぬき。
その昔のメタボ兄弟の寺田さんと、ひと石ずつ踏みしめるの図。
本堂には「長生きできる水」もあり。「心の甘露水」とは名コピー!
やっぱり水! 良いお酒には水が欠かせません。酒の80%くらいは水。身体も水が65%といいますね。お酒を飲むときも水を一緒にとると、悪酔いしません。
長生きの水をかみしめて飲む。
カメの位置が絶妙だと感心したやまよであった。
萩の花も満開の魚沼でした。
越後湯沢駅にあるぽんしゅ館の人気の人形。こうなる前に水も一緒に…。
新潟 鶴齢さん初呑みきり会
September 13, 2008鶴齢さんの初呑みきり会に参加。新幹線Maxに乗り越後湯沢で下車すると、社長の青木貴史さんがお迎えに。まずは「しんばし」というお蕎麦屋さんで、新潟産の蕎麦粉を使用したへぎ蕎麦(海藻のフノリでつないである蕎麦)をいただきました。こちらのお店の野菜はほとんどが自家栽培だそうです。
ネギもたっぷりワイルド、みずみずしさも充分。天ぷら一番手前は塩沢名産の舞茸です。肉厚で香りも抜群。
名物の「不動もち」。よもぎをこれでもかと使った濃い〜よもぎ味。
青木酒造入り口です。雪深い地ゆえ、蔵の前は雁木がずっと。風情あります。
左)今季のつくりは早く、9月18日から。蔵人さん準備に大わらわ。
右)貯蔵酒タンクの蓋部分。大吟醸は3度ぐらいに冷蔵keep。
米や酒の移動に使うホースです。最近、新調したばかり。清潔感いっぱい。
左)青木酒造さんは火事の経験あり。蔵はその時、全焼に。唯一残った写真の蔵も天井下の梁は炭のごとく真っ黒。その後の地震で外壁にもダメージが…。今は自家用の漬け物保存場。とはいえ、蔵は強し!
右)今回のびっくり。青木さんのお隣はお姉様かとおもいきや、母君と聞いてたまげました。おしゃれでスレンダーなママ。壁材から床の石選び、配置などインテリアを担当しています。
びっくりその2。庭の池。水がとってもきれい。蔵の地下水を注ぎ、溢れると川へ流れでる仕組みとか。なるほどそれで透明なのかとふむふむ。
なのですが鯉の姿はどこにもみえず。誰もいない池!?
なんでも地下水を入れるようになったら、水が冷たすぎて鯉には不向きと判明。
よくよくみると、池の隅っこの方にお子さんが祭りですくったという金魚が2匹ほどいました。金魚強し。
さて、いよいよ会の時間。場所は「龍言」です。豪農の家を移築したという建物。
セミナー会場。味があります。日本酒といえば、やっぱり畳ですね!
お待ちかね。勉強会終了後は懇親会!中央がどどんと空いたレイアウトで広々した宴会場。青木酒造の阿部さん法被で活躍中。
契約栽培の酒米「越淡麗 」を使ったお酒、低温で丁寧に発酵させたきれい系など自信作が勢揃い。タンクからこの日のために詰めてきた発売前のお酒で乾杯!
杜氏の新保さん、人格者です。青木さんが注ぎ、杜氏さんがお返しに注ぐの図。酒づくりは信頼関係あってこそ。
さて、肴です。地のものがずらりと並びました。鮎の塩焼き。そして初めて食べたイワナの洗い。水のようなするりとした味! みょうがときゅうりの極せん切りであえてあり、レモンもよし、醤油もよし。鮮度の良いイワナはこう食べるのかと勉強になりました。
左)北前船で流通したニシンは、この地の人にとってソウルフード。酢でしめた大根と一緒に。
右)龍言のおかみさんです「鶴齢はおいしいわね」
きのこたっぷり汁。海藻入りはお約束の麺。
青木さんありがとう!
ひとくちに新潟で醸す酒といっても千差万別。「新潟はタンレイ
カラクチ」とよく言われますが、青木酒造は生産の8割が地元需要で、それこそニシンに合うような、うまみのあるお酒がメイン。地元で愛され、消費されてこそ地酒ですね。
「越淡麗 」という新潟で開発された酒米は、その文字面から、淡くすっきり系の酒ができる気がしますが、青木酒造の場合、文字から想像する”端麗”ではなく、どちらかといえばうまみを併せ持つしっかり系の感あり。飲んでみなくちゃわかりません。
一同に少しずつ味わうと、米やつくりの違いがよくわかります。日本酒とひとくくりにしてはいけないほどバラエティ豊か。日本酒はひとつではないし、ひとつの蔵の酒でさえ、ひとつにはくくれない。改めてお酒の懐の深さを感じました。それから先入観をもたないこと。飲むときは中庸の精神で。
楽しく、おいしく日本酒にふれあった会でした。青木酒造の皆様お世話になりました!